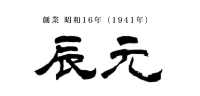Geo Story
千年の歴史がある「しもつかれ」
しもつかれは、栃木県を中心に食べられている郷土料理で、千年の歴史があると言われています。毎年二月の初午の時期に各家庭でつくる風習があり、稲荷神社にも御供えする行事食でもあります。
材料は一般的に、酒粕・鮭の頭・大豆・大根・人参になりますが、各家庭によって入れるものも味付けも違うのが特徴です。
鬼おろしで大根、にんじんを刻み、他の材料と一緒に鍋で煮込み、数日発酵させて食べます。
しもつかれは、江戸時代にそれまで捨てられてしまっていたものを再活用することで現在の形になったと言われています。
現代は飽食の時代で食べ物が手に入れやすくなった分、廃棄される量も増えました。日本では、毎日おにぎりを国民がひとり1つ捨てている量と同量の食べ物が廃棄されているデータもあります。これらが可燃処理されるゴミの量を増加させ、地球温暖へと繋がるCO2を大量に排出させる原因ともなっています。
室町時代に日本で生まれた「もったいない」という言葉は、2004年にノーベル平和賞を受賞したワンガリ・マータイさんによって「MOTTAINAI」として世界の共通言語となりました。
世界的に価値あるものとして認められた日本人の精神性。しもつかれはその「もったいない精神」から生まれた料理そのものです。これは日本人が誇るべき価値を持ち合わせた料理と言っても過言ではありません。



もったいない精神
しもつかれが現在の形になったのは、江戸時代の飢饉を乗り越えるために、廃棄されていた食物を集め、なんとか命を繋ぐためだったという説があります。現代は飽食の時代で多くの食べ物が捨てられていることから、このもったいない精神はサステブナルそのものです。
お裾分け文化自分でつくったしもつかれを、重箱に入れ近所におすそ分けする文化があります。自分だけで消費するのではなく、地域と「共存」する精神があります。現代の「シェアリングエコノミー」の精神性に通じる文化です。「七軒食べれば無病息災」とも言われています。
個性を尊重し、違いを認め合う
しもつかれは、地域や作る人によって材料や工程が異なります。他人がつくったものを否定するのではなく、個性を尊重し認め合い、味の違いを楽しむ文化が県民に根付いていたと推察されます。まさに現代に通じる「多様性」「ダイバーシティ」の精神性そのものです。
栄養価が高い発酵食栄養価の高い材料に加え、酒粕が入るため発酵食でもあります。今後予防医療に向かう社会において、しもつかれの栄養価と消化の良さは相性が良いと考えます。栃木らしい伝統医療食として県内のみに関わらず、県外・世界にも知っていただけるような活動をします。


究極のジオガストロノミー
しもつかれは日本が誇るサステナビリティな郷土食です。
フードロスを解決するヒントとして、しもつかれが1000年繋いできた精神性は、時間も距離も超える「究極のジオガストロノミー」と言えるのではないでしょうか。
しもつかれブランド会議
代表
青 柳 徹
しもつかれブランド会議
青 柳 徹